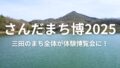兵庫県三田市にある欣勝寺(きんしょうじ)では、さんだまち博の期間中、坐禅体験プログラムが開催されていました。今回の開催日は2025年10月11日(土)で終了していますが、欣勝寺では都度坐禅体験を実施しているとのこと。参加希望の方は公式HPや電話で開催日や予約方法を確認してください。
坐禅体験の概要
坐禅体験は、初めての方でも安心して参加できる内容です。心を落ち着け、日常を離れた静かな時間を過ごすことで、新しい自分を発見できるのが魅力です。プログラムでは坐禅の基本動作の説明に加え、三田の民話「くわばらくわばら欣勝寺」の紙芝居や写経も体験できます。
- 会場:曹洞宗 欣勝寺(きんしょうじ)
- アクセス:JR三田駅から徒歩または車で約12分、駐車場無料(約15台)
- 参加料金:大人1000円、子ども(6歳~12歳)500円
- 定員:20名
- 対象:6歳以上
- 服装:ゆったりした動きやすい服装、スカートは不可
- 申込方法:事前予約制(公式サイトやフォームから5日前まで、先着順)
※今回紹介したプログラムは終了しています。今後の参加希望は公式HPやお問い合わせで確認してください。
➡️ 公式サイトはこちら https://www.kinsyoji.jp/
坐禅とは

坐禅は、心を落ち着けて「今この瞬間」に意識を集中させる禅の修行です。座って呼吸に意識を向けることで雑念を手放し、心身をリセットできます。初めての方でも簡単に体験でき、日常のストレス解消や集中力向上にも効果的です。
欣勝寺について

欣勝寺は三田市にある歴史ある曹洞宗の寺院で、山間の静かな環境に位置しています。境内には伝統的な建物や庭園が広がり、落ち着いた雰囲気の中で坐禅や写経などを体験できます。地域の民話「くわばらくわばら欣勝寺」の伝承も残り、文化や歴史を感じながらの体験が魅力です。
欣勝寺に伝わる民話「くわばらくわばら欣勝寺」は、雷除けの伝承として三田市で語り継がれてきたお話です。昔、村人たちが雷に悩まされていた際、欣勝寺の和尚さんの知恵と祈りによって村を守ったという内容で、紙芝居ではそのユーモラスで心温まるエピソードを楽しむことができます。この民話を知ると、坐禅や写経を体験しながら感じる寺の空気や歴史もより深く理解できます。
詳しくは公式サイトに掲載されています。➡️ https://www.kinsyoji.jp/#ind-kuwabara

プログラムの流れ(当日の体験)
- 坐禅の説明・御本尊へのご挨拶
法要の簡単な説明や合掌、お焼香を通じて、心の準備をします。 - 坐禅体験
両足を組む結跏趺坐(けっかふざ)や片足を組む半跏趺坐(はんかふざ)で座り、手は膝の上で法界定印を組みます。背筋を伸ばし肩の力を抜き、目は半眼で前方を軽く見ます。腹式呼吸をゆっくり繰り返し、呼吸や「今ここ」の状態に集中します。雑念が浮かんでも判断せず自然に流すのがポイントです。 体験は約10分間の座禅+歩行瞑想(経行)5分+再度座禅15分。希望者は警策(板で肩を軽く叩いてもらう作法)も体験できます。私も一度お願いして、痛かったけど集中力が戻る感覚が印象的でした。 - 写経体験
椅子に座って机の上で筆ペンを使い、般若心経を写します。願い事を書き込んでそのまま納めるか、持ち帰ることも可能です。 - 紙芝居「くわばらくわばら欣勝寺」
雷除けの伝承として三田市に伝わる民話を紙芝居で学べます。若和尚さんの語りが優しく、参加者全員が引き込まれる時間でした。
坐禅体験の詳細
最初に和尚さんから、姿勢や呼吸、心の持ち方について丁寧な説明がありました。
坐禅は体が固いとしんどくなるとのことで、まずは軽く全身のストレッチから始まります。
「背筋をまっすぐに、上からつられているようなイメージで」との言葉に合わせ、体を少し横に揺らして軸を整えます。
呼吸をしっかり意識すること、そして「できるだけ無でいられるように意識してみましょう」という言葉が印象的でした。
坐る場所は御本尊様の前。畳の上に、丸くて厚みのある坐禅専用の座布団「坐蒲(ざふ)」が用意されています。(参考:https://amzn.asia/d/gdXRlI1)
明るく静かな空間で、畳と御香の香り、涼しい風が心地よく流れていました。

実際に座ってみると、坐蒲が体をしっかり支えてくれるため思ったよりも楽に座れます。
ただし、しばらくすると足がじわじわとしびれてきます。そこで行うのが「経行(きんひん)」と呼ばれる歩く瞑想です。
坐禅が始まる前に練習があり、初めはぎこちなかった動作も、実際に坐禅を体験した後に行うと自然に体が流れに乗るように感じられました。
歩く速度はとてもゆっくりで、前の人のペースに合わせて一歩ずつ進みます。
足のしびれも次第に和らぎ、呼吸と歩調が合うと心まで穏やかになります。
希望者は「警策(けいさく)」と呼ばれる作法も体験できます。(参考:https://amzn.asia/d/iiQm994)
これは、肩を軽く板で叩いてもらうことで集中を取り戻すもの。
私も2回目の坐禅で合掌をしてお願いしました。若住職さんが後ろに立ち、肩に板を添えて「パシン!」と音が響きます。
叩かれた瞬間はじんと痛みが広がりますが、気持ちは不思議とすっと引き締まりました。
Tシャツより少し厚めの服でこの感覚だったので、薄い服の場合はもう少し痛く感じるかもしれませんが、悶えるほどではなく本当に目が覚めるような体験です。

坐禅の間は、御香と畳の香り、そして風の音や鳥の声が穏やかに響きます。
無を意識していても、ふと気づくといろんな考えが浮かびます。
そのたびに「また無に戻ろう」と姿勢を正して呼吸を意識すると、少しずつ心が軽くなるような感覚がありました。
坐禅体験で感じたこと
今回の参加者は大人3名。
初めての坐禅ということで少し緊張もありましたが、和尚さんの穏やかな声かけと、たまにお部屋に入ってくるチワワのわんちゃんの存在が心を和ませてくれました(わんちゃんがいたのは体験の前後で、体験中はお外にいました)。
静かな本堂の中で呼吸に意識を向けるうちに、少しずつ心が落ち着いていくのを感じます。雑念が浮かんでも、それを無理に消そうとせず、自然に手放していく——そんな時間が新鮮でした。
坐禅を通して得られたのは、「心が静まる」というよりも、「余分なものが削ぎ落ちて、集中が自然に戻っていく」感覚。
それは日常の中ではなかなか味わえない、貴重な体験でした。
写経や紙芝居も印象的で、普段の生活では触れることの少ない文化や歴史に触れる時間。
一つひとつの所作が丁寧で、心が満たされるような静けさがありました。
普段スマートフォンに触れてばかりの私にとって、「何も考えず、ただ坐る」という行為はとても新鮮でした。
理屈では説明できないけれど、体験を終えて帰るころには、頭の中がすっきりと整い、心が少し軽くなっていました。
「またこの静かな時間を味わいたい」——そう思える、穏やかで深いひとときでした。

坐禅体験のポイント
- 初めてでも丁寧に教えてもらえる
- 坐禅+写経+民話の紙芝居で五感で楽しめる
- 希望すれば警策体験も可能
- 静かな山の中のお寺で、心身ともにリフレッシュ
坐禅体験は、単に座るだけでなく、集中力や心の落ち着きを取り戻す良い機会になります。参加後は、普段の生活でも呼吸や姿勢を意識したくなるような感覚が残ります。
まとめ
欣勝寺の坐禅体験は、初めての方でも安心して参加でき、心を落ち着ける貴重な時間を過ごせます。三田の民話や写経も体験できるため、文化や歴史に触れつつ、自分自身と向き合うことができます。今回のプログラムは終了していますが、今後体験したい方は公式HPやお問い合わせで開催日や予約方法を確認してください。

⬇️ このプログラムが行われたイベント「さんだまち博2025」の記事はこちら